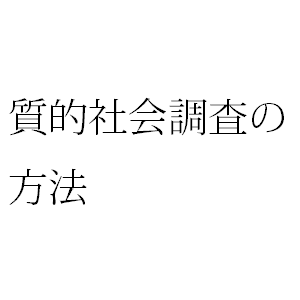岸政彦先生から『質的社会調査の方法』をいただいたのは出版直後だと思うので、読みたいと思いつつ3か月も寝かせてしまった。もらった日に「あとがき」と岸さんの章のごく一部だけ読んでしまい「ああ、良い本だ」と感じてしまったのが良くなかった。
僕も駆け出しとはいえ、実は論文では「生活史」を用いていると常に書いているし、質的調査について教えたり書いたりしていることもある。とはいえ、生活史そのものは魅力的でも、それを魅力的に表現するだけの理論も技術も知識もまだまだ足りないという自覚がある。だから、良い本からどこか逃避したかった。
が、子どもではなく、プロフェッショナルとして食べている身なので、3か月でそこらの気持ちは整理を付けて読んでみた。良い本だった。

著者の岸さんは、2012年に僕が赴任したときには既に龍谷大学社会学部にいたので、これまで丸5年、同じ職場の同僚だ。とはいえ、不思議なことに学科の壁みたいなものがあり、仕事でご一緒したことはほとんどない。
最初に名前を知ったのはジョック・ヤングの訳者に入っていたから。同僚になり『街の人生』が出たときに感銘を受けて、ゼミ生全員に購入を指示し、読んだ上で宿題として自分で誰かの「街の人生」を聞いてくるようにと言った。それを文字起こししたものを準備して岸さんにゼミでゲスト講師を務めてもらったのは、今考えても贅沢な時間だった。
また、著者の石岡丈昇さんは、社会理論・動態研究所が主宰するアジア社会学研究会に僕が参加させてもらっていたとき(今も参加したいのだけど、日程が合わない……)に知り合った。僕が育った札幌に戻ったときには、北大構内を案内していただいたこともある。
僕は博士課程まではフィリピンの都市貧困層で生活史調査をしていたのだけど、たぶん石岡さんに会ったころはもうほぼ「フィリピン研究」を僕がやめてしまった後だった。
もう一人の著者である丸山里美さんとは面識がない。
さて、著者と僕との関係はいいとして。この本は副題に「他者の合理性の理解社会学」とある。
社会学、特に質的調査にもとづく社会学の、もっとも重要な目的は、私たちとは縁のない人びとの、「一見すると」不合理な行為の背後にある「他者の合理性」を、誰にもわかるかたちで記述し、説明し、解釈することにあります。
このまとめに「そうか、こう表現すればいいのか」と悔しく思った。「合理性」という言葉を用いて、よく授業で「合理性というのは経済合理性だけではないし、僕にとっての合理と、あなたにとっての合理は違う」というような話し方でよく使っていた。その違うことに接近し記述・説明・解釈することこそが社会学の目的だと言われると、僕が社会学に関心を持つのは当たり前なようにも思えてきた。
自分や第3者にわかる(合理である)かたちで示せるのは、もはや他者の合理性ではないのではないか、と一瞬突っ込みたくなる。ただ、ここで「一見すると」とあるように、合理的であるように見えるかどうかは案外、一見したときの印象に過ぎず、記述が可能なのかもしれない。それでも当然、記述はできても説明・解釈ができないというか、いわゆる共約不可能の問題が出てくるような気もする。
簡単に「わかった」と言ってしまうのは、とても暴力的なことです。
しかし同時にまた、私たちは私たちの隣にいる「他者」の人びとを、なんとかして理解しようとする営みをあきらめてしまってはいけません。
まさに、こういうことなのだ。「本当にわかった」などということはないが、それがないということと、わかろうとする行為をとるかどうかは異なることだ。
さて、この本、読み進めていく間に何度も励まされることがあった。「そっか、それでいいのか」「こういう悩みって僕だけじゃないのか」とか。
お酒が強くない人やたばこが吸えない人は調査に向いていないのかというと、もちろんそんなことはないでしょう。それは調査者の数ある個性のうちの一つにすぎず、その人なりの個性をいかした、別のやり方の調査をすることになるというだけです。
そう、それだけのことです。授業でも「インタビューの巧拙みたいなものは、もしかしたらあるのかもしれないし、方法は学んだ方が良い。でも、僕がやるよりも初学者の受講生がやる方が豊かな語りが聞けることも多い」という話を僕もする(ただし、「良い語り」を聞けることと研究に繋げられるかどうかはイコールではない)。
「え、調査やっているのに酒もタバコもダメなの?飲みにケーションできなかったら、深いところまで全然聞けないでしょ。ガハハ」的なオジサマたちを冷ややかにあしらってきたこの10年間。「丸山さんを読んでください」と今なら言える。
そういえば、丸山里美さんは次のようなことも言っている。
同じ人に質問をすれば同じ回答が返ってくるというような、暗黙のうちにある客観主義的な前提が、はっきりしたわかりやすい声をあげにくい状態に置かれている少数者の排除につながってきたのではないか。
よくわかる。同じ人がほかならぬその人についてのことであっても、異なる回答をするのは質的調査を一度でもやったことがあるなら気づくべきことだ。ところで、僕自身は「同じ人に何度も(最低2回は)語りを聞く」ということを自身の方法(論)としていて、ほぼすべての調査について実践している。僕の場合は毎回の語りで「矛盾」や「葛藤」が生じる箇所について調査を展開していくが、丸山さんの場合は毎回の語りで共通するところを中心に展開するらしく、そういう方法もあるのかと勉強になる。
石岡さんは「人びと」ではなく「人びとの対峙する世界」を知ることが参与観察のねらいだと書いている。参与観察、なかなか僕には難しそうだけど、いつかやってみたい気もする。
取り上げられたテーマに基づく対話型調査を通じて、「人びと」を知るのではなく、「人びとの対峙する世界」を知ること、そしてその世界が調査者と被調査者の双方に意識化されることこそがフレイレによる実践の核心でした。
これを読んで、僕が挑戦してみたいのは、パウロ・フレイレ的実践なのかもしれないとも気づくことができた。今、書き始めている単著は質的調査法に関することと、こうした「実践」に関することの両方を書こうとしているので、もし無事に書き上げられたら、著者のお三方に送って、批判していただきたい。