日本生活学会・生活学プロジェクト(2016年度)に採択され、左義長の調査をしている。今回、僕にとっては民俗調査の手習いのようなことでもあり、概念枠組を手に入れる前にプロジェクトを構想しまずは調査してみている。
僕はある地域で左義長という伝統行事が変遷してきた過程を調査すれば、都度の変化ごとに地域の意思決定・選択が成されているはずだと考えた。2つの隣接する地域で変遷を追うことで、地域ごとに価値づけが異なることが明らかになるはずだ。
とはいえ、まだ十分にはそのあたりはわかっていなくて、「そろそろ民俗学でどう言われているか学んでみるか」と思ったところ気になる本を見つけた(こんな行き当たりばったりの研究の方法、ゼミの学生がしようとしたら寛い心で見守ることができるだろうか)。
金賢貞が2007年に博論として書いたものに加筆して2013年に出版された『「創られた伝統」と生きる:地方社会のアイデンティティ』は、茨城県の「石岡のおまつり」を事例とした伝統化に関する研究成果だ。
タイトルでは当然、ホブスボウムを想起するものの「創られた伝統」はキーワードとは思えない(博論のタイトルにも含まれていないようだ)。むしろ副題の「地方社会のアイデンティティ」こそが主題だと思う。そして、全編が石岡にかかわることなので、なぜタイトルに石岡が入っていないのかは読み終えてもよくわからない(もったいない)。創られた伝統と生きる、というよりは、伝統を創りながら生きるというのが読後の印象だ。
本書で言及されている「中央と周縁」という描き方の重要性・妥当性はいまいちわからなかったが、書評を読む限り、やはりそこもポイントのようなので僕の読み方が足りないのだろう。
さて、本書ではローカル・アイデンティティを「地域社会の独自性を主張する集合的認識」としている。「集合的認識」というのがおもしろい。この記事の冒頭で示した僕の左義長調査に関する興味関心と繋がる。ただ、アイデンティティという語を選んだ以上、独自性という言葉が出てくるのは避けようがないかもしれないが、僕が「地域ごとの価値づけ」としているのは独自性の主張という観点ではないので、この概念はそのままは用いることができなそうだ。
著者のフィールドワークは史資料も語りも充実していて読むのが楽しい。とりわけ、個人の語りへ着目する手法が、やはり僕自身の左義長調査の参考になる。
「個人のレベルまで微分することに有効性」を認める民俗芸能研究も現れるようになった。これは、最近のライフヒストリーという方法論の認識とも相通じる。つまり、ある特定の個人の思想や価値観、社会的属性などにフォーカスを合わせることで、本質的な実在物としての民俗芸能ではなく、社会的諸条件に敏感に反応しながら、いまを生きている民俗芸能のむき出しのあり方を浮き彫りにすることができるのだ。
このようにして、特定の個人に注目することの正当性が「きわめて有効かつ重要な方法」として主張される。ただし、著者は「すべての個人を主体として捉えるわけではない」という。
社会構造や社会的諸条件に常に影響され、反応し、規定し合う存在としての主体のなかでも、社会的事実としてのある現象における因果関係を理解するうえで欠かせない存在もしくは台風の目のようにその中核を占める存在をコア・アクター(core actor)として位置づけし、その実践を具体的に見ていく。
このようにして描かれるコア・アクターたちの語りや足跡はどれも読み応え十分で、確かに重要であることはわかるのだが、その限定がなぜ可能なのかは僕にはわからない。たとえば社会的事実の「因果関係を理解するうえで欠かせない存在」や「中核」など本当に抽出可能だろうか。あるいは社会的事実としての現象の設定はどのように妥当性を持つのだろうか。
終章で著者は言う。
日常的な消費行動とは違い、アイデンティティーは日常的に表出するものではない。さらに、アイデンティティーは、一個人だけで決まるものでもない。常に他者や外部世界を必要とする関係性の概念なのであり、その関係の微妙な力学によって揺れ動き、修正され確認・強化される意識のあり方なのである。
ここで語られているアイデンティティはもちろんローカル・アイデンティティのことだろう。一個人だけで決まるものではないが、その決定過程にはやはりコア・アクターが(他の個人より)方向付けの面で強い影響力を保ったのだろうか。
もう一つ、アイデンティティは「日常的に表出するものではない」のだろうか。消費行為分析への批判的な立ち位置を示すことは理解できる。しかし、伝統行事等の場面で強く表出されたり主題化されたりするローカル・アイデンティティは、集合的な認識である以上、日常的にも相対的には弱くとも表出されるのではないだろうか。
M. シンガーの論を踏まえて展開している伝統化に関する議論は、僕の左義長調査を基にした研究にも適用できそうだ。
シンガーの伝統化論は、土着の既存の文化要素をAとし、異質で新米の文化要素をBとするなら、再統合された結果としての伝統Cとの関係を、A+B=Cというふうに単純化したところに問題がある。
シンガーが見落とした問題、Bがすべて同じレベルのBではなく、Aより下位レベル、言い換えれば、Aに含まれ、手段的な意味の強いbがあり、これを含めて伝統化を論じなければならないのである。
なるほど。左義長調査において、隣接する2つの地域がそれぞれ、竹を組んだり引っ張り上げたりするのに使うのが「藤蔓」か「針金」か、あるいは左義長を「1/14の夜に実施するか」、「1/15に近い土日に実施するか」といった点についてどうして違いがあるのかという問題があった。本書のこの議論に則れば、2つの地域において、「Bとするか、bとするか」の価値判断が異なったということになる。
では、Bとbを区別するものは何か。それは、Aを「伝統」と見なす認識や言説実践、規制の仕組みであり、石岡では總社宮大祭を規定する「古い歴史と伝統のまち」というローカル・アイデンティティーがそれなのである。
実は「古い歴史と伝統のまち」というローカル・アイデンティティ(というよりコンセプトに見える)があってもなお、「何がBかbか」つまり何が伝統や地域をそれとして成り立たせるかは自明ではないが、こうした議論の展開はたいへん参考になった。
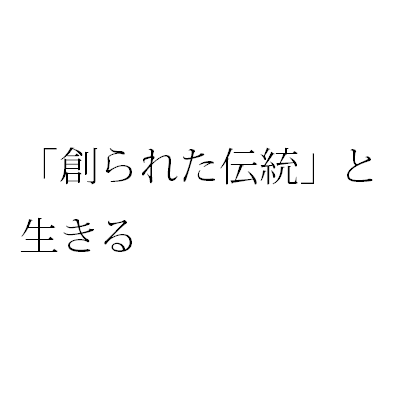

One Reply to “金賢貞『「創られた伝統」と生きる』”