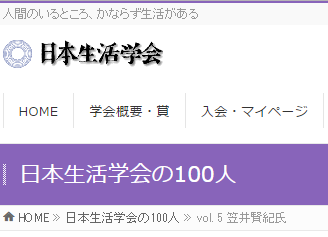2016年に加入した日本生活学会の公式ウェブサイト内コーナー「日本生活学会の100人」に私がインタビューされた記事が公開されました。
「語りから未来を紡ぐ方法論の探究」というタイトルです。学部生のときに何かの本で読んで、これを目指してみようと思った「ハイブリッド研究者」(井上真)のことも少し紹介しました。「一人学際」というおもしろい発想ですね。
私は、いろいろな調査・研究に取り組んでいますが、今回の左義長調査は率直に言えば「地味」なものだと思います。対象は全国どこにでも見られる(そして全国的におそらく担い手は減ってきている)民俗行事ですし、インタビューにほぼ依存した方法をとりました。
そもそも、私の関心はおおよそ「ふつう」の人たちに向いています。「どこにでもある」対象にアプローチするからこそ、質的調査が活きてくる場面もあります。
重視されるのは、内容をありきたりのカテゴリーに落とし込んでしまうのではなく、むしろ質的な多様性――つまり、ある1つの現象がもつ多くの差異やバラエティ――を表現するような、ニュアンスに富んだ記述を行うことである。(クヴァール, 2016訳『質的研究のための「インター・ビュー」』)
特に院生のときには学会発表などで「もっと代表性の高い事例がある」「この事例のどこが先進性があると言えるのか」というコメントを批判的にいただきました。特異な突出した事例を扱うことによる研究上の意義はわからなくもありませんが、私のやろうとしていないことをコメントされてもなあ、と感じることが多かったです。
「ということは、典型的な事例としてこれを挙げているということですね」というコメントは、まだ理解ができるものでした。ただ、1事例を深く調べて記述すれば当然、他事例との差異が浮き彫りになりますし、その1事例をもって「典型的である(から研究上の意義がある)」というのは乱暴ですから、やはり何のためのコメントかと釈然としないこともあります。
さて…、私の左義長の調査は「正しい左義長のあり方」を模索したものではなく、また「現在の民俗を記録」しようとしたものでもありません。

左義長がこの数十年だけでもさまざまな変化を遂げており、この変化と地域の生活の変化とはつながっているという仮説のもと、(1)左義長の変化から生活様式の変化を明らかにする(という方法を導く)ことを一つ目の目的にしました。整理は必要ですが、これはそこそこ満たせそうです。
次に、左義長の変化は地域によって異なるため、(2)左義長の変化から地域の価値付けを明らかにする(という方法を導く)ことを二つ目の目的にしました。これはなかなかうまくいっていません。
そして、調査の中で副次的に、実は左義長が住民自治へとつながる地域・住民関係の入り口として重要な位置づけができるのではないか、という考えにたどり着きました。
「長く続いてきたから左義長を失ってはいけない」という情緒的な発想には、その負担や位置づけを考えると手放しには賛成できませんが、それでも一考の価値はありそうです。
左義長が住民自治へとつながる生き方のモデルコースの入り口となっていたものの、そのモデルコース自体が崩れているというのが現状です。では、現代社会において、地域と住民との関わりはどのようなものが要請されるべきで、そのためにはどのような仕掛け(過去に左義長が果たしたような。)があるとよいのでしょう。
そこで編み出されるモデルコース(あるいはモデルコースがあること自体が現代的ではないという帰結?)に、左義長がコンテンツとしてまだ活かせるのであれば、失わせない方がいいでしょう。「続いてきたという事実」が持つ力は一定強いものがあります。
▼日本生活学会の100人 http://lifology.jp/people100/vol005kasai/